こころの科学175号 日本評論社 2014年5月
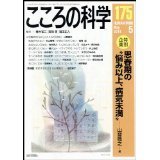
わが敬愛する精神科医 山登敬之先生(東京えびすさまクリニック)の企画による特集「思春期の“悩み以上、病気未満”」は、さすが!!と言いたくなるような内容満載でした。
企画・編者のことばとして
「精神科医の目から見れば、思春期の年代には、病気の輪郭が曖昧なケースが少なくない。また、慌てて白黒をつけるよりも、グレーはグレーのまま経過をみたほうが、のちに本人に利益をもたらす場合もある。この時期、そんな子どもの傍らには、彼らの悩みに耳を傾け、適切な助言のできる大人が一人でも多くいてほしい」
とある所に、山登先生の立ち位置が現れていると思いました。
記事の内容は
勉強ができない・学校に行きたくない・友だちという存在・いじめにあっている・家に帰りたくない・イライラする、キレてしまう・ケータイ依存・友だち未満、恋人以上!?・性への違和感・自分がどう見られているか気になる・自分のことがイヤでたまらない・リストカット、OD(薬物依存)・死にたくなる・大人になりたくない?
と多岐にわたります。
「友だちという存在」(岩井秀人氏)から、心に残った一節。
他者とこころ同士のつながりをもつきっかけとなるのは、自分が「何ができる」とか「何をもっている」というようなこころの中の「強い部分」ではなく、「何ができない」とか「何をもっていない」という、こころの「弱い部分」だと思っている。
「お互いひどい目にあってきたけど、まあ、頑張ろーよね!」という関係。生きてきた中で遭遇した理不尽なことというのは、時を超えて意外なところで人と人を結びつける。それを共有できたとき、「えー! 自分だけじゃなかったのー! あなたも大変だったのねけ!」とお互いにその理不尽さを共有できる。
この「共有できる」ということがとても救いで、一人でもちきれないものだって、何人かでもてば軽くなるものだ」 P26
